三国志武将の異名・通り名

武将さんたちの異名や通り名を集めてみました
ここに乗ってないものがあれば教えてください

悪来
(あくらい)
曹操の警護を務めた典韋の異名。
「悪来」は古の豪傑の名。典韋の怪力を見た曹操が
「まるで古の豪傑・悪来のようだ」と言ったことに
由来する
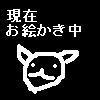
阿斗
(あと)
劉備の息子・劉禅の幼名。現在も「阿斗」は
無能の代名詞となっている

阿瞞
(あまん)
曹操の幼名。瞞は「欺く、騙す」という意味で
「嘘つきちゃん」といった感じ

阿蒙
(あもう)
呂蒙の幼名。呂蒙は勉強せず毎日喧嘩に明け暮れる日々を
送ったので「呉下の阿蒙」(無学の暴れん坊)と人々は呂蒙を
馬鹿にした。その呂蒙は後年、猛勉強をして呉を支えるほどの
人物になった。このことから「呉下の阿蒙に非ず」「士、別れて
三日、即ち刮目して相待つべし」という故事が生まれた

燕人
(えんひと)
張飛の住んでいた地域は古くは「燕」という国
だったことから、張飛は自らを燕人と呼んだ

大耳(児)
(おおみみ/だいじじ)
劉備は手が膝まで届くほど長く、自分で見ることができるほど
大きい耳をもっていたという。劉備を「大耳!」と罵った呂布曰く、
「奴は人間ではない。ミミデカテナガゲントクという新種の生物だ」
とのこと

臥龍/伏竜
(がりょう/ふくりゅう)
諸葛亮のあだ名。司馬徽は諸葛亮とホウ統を高く評価し
2人を「臥龍鳳雛」と呼んだことに由来する

陥陣営
(かんじんえい)
呂布軍配下最強を謳われた高順の部隊の異名。高順の部隊に狙われた
陣は確実に壊滅したといわれ、敵から「陥陣営」と呼ばれ恐れられた





魏の五将軍
(ぎのしょうぐん)
魏の猛将・張遼、張コウ、于禁、楽進、徐晃の五人のこと
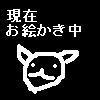
黄髯
(きひげ)
曹操の息子の曹彰は自ら猛獣と戦うほど腕力に優れていた。
曹彰は髯が黄色かった事から曹操は曹彰を「黄髯」と呼び
可愛がった
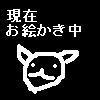
弓腰姫
(きゅうようき)
孫権の妹・孫尚香は男勝りの性格で武芸を好み、常に腰に
小さな弓を携えていた。そのためこのような名で呼ばれた

錦馬超
(きんばちょう)
西涼の雄・馬超の持つ凄まじいカリスマ性から、人々は馬超を
「まさに錦のようだ」と褒め讃えたことに由来する。
「馬超殿はスターじゃ!」「スター錦野じゃ!」と異民族が
叫んだ言葉が縮まり「錦馬超」になったという異説もある

建安七子
(けんあんしちし)
建安の時代、曹操を中心に文学は大きく発展した。
その中において特に優れた活躍を見せた孔融・陳琳
王粲・徐幹・阮ウ・応トウ・劉テイの七人がこう呼ばれた





五虎将軍
(ごこしょうぐん)
劉備配下の関羽・張飛・趙雲・黄忠・馬超の五人のこと
この名前は「演義」にしか登場しない

虎痴
(こち)
魏の豪傑・許チョの異名。普段はボーッとしているが、
いざとなると猛虎の如き活躍をすることからこう呼ばれた

十常侍
(じゅうじょうじ)
後漢末期に張譲、趙忠ら宦官が皇帝を意のままに操り政治を支配した。
彼ら(?)の役職名が「中常侍」だったことから、特に権力を持った
十人を「十常侍」と呼ぶようになった

小覇王
(しょうはおう)
僅か数年で江東を制した若き孫策を讃えた名。
「覇王」は楚の項羽のこと。項羽の如き進撃を
見せる孫策を人々はこう呼んだ

人公将軍
(じんこうしょうぐん)
黄巾賊と呼ばれた「太平道」のNO.3・張梁のこと
「人公将軍」は漢王朝の将軍号ではない

水鏡先生
(すいきょうせんせい)
荊州の大学者・司馬徽の異名
⇒好好先生

大賢良師
(たいけんりょうし)
黄巾賊と呼ばれた「太平道」のNO.1・張角のこと
⇒「天公将軍」

竹林の七賢
(ちくりんのしちけん)
当時の行き過ぎた儒教的礼節を真っ向から批判した
阮籍、ケイ康、山濤、劉伶、阮咸、向秀、王戎の七人のこと

地公将軍
(ちこうしょうぐん)
黄巾賊と呼ばれた「太平道」のNO.2・張宝のこと
「地公将軍」は漢王朝の将軍号ではない

程公
(ていこう)
孫堅の代から呉に仕えた程普のこと
最古参の程普を人々は敬意を込めてこう呼んだ

東呉の徳王
(とうごのとくおう)
孫策に滅ぼされた豪族・厳白虎が名乗った名
名前のわりに徳が無いと専らの噂
更に進軍
TOP



